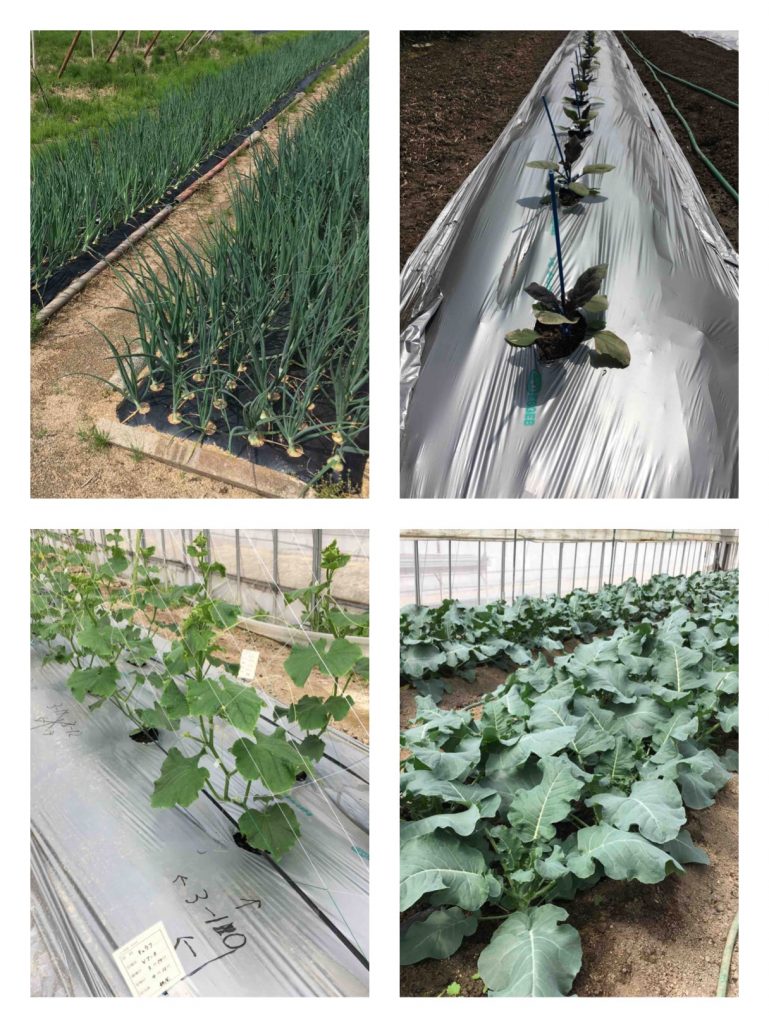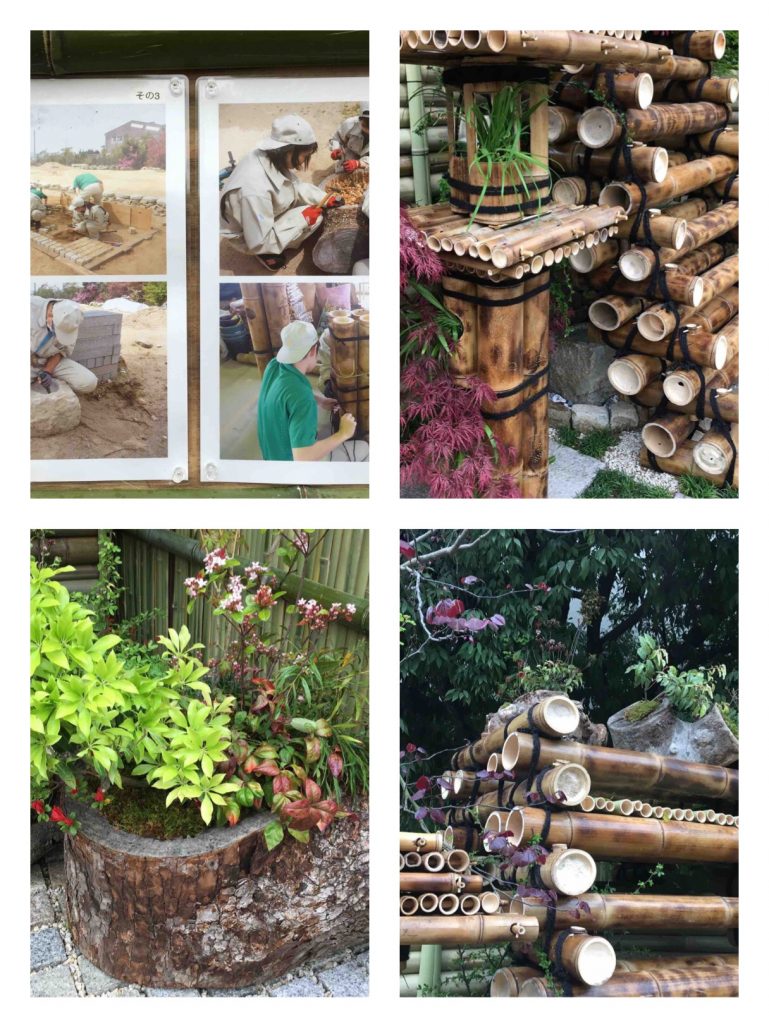5月29日、蒜山にある中四国酪農大学を会場に 農業クラブ家畜審査競技 乳牛の部が行われ、個人の部で農業科2年の西田建太さんが最優秀賞を受賞しました。また、団体の部で(農業科3年 荒川万里奈さん、細川美雨さん、農業科2年 西田建太さん、増田彩良さん、村山莉子さん、農業科1年生 三宅芽依さん)最優秀賞とダブル受賞と素晴らしい結果を残してくれました。おめでとうございます。なお、この大会に参加するにあたってご協力いただきました「みさお牧場」に感謝申し上げます。地域に出かけて学習したこと、仲間と一緒挑戦したことは素晴らしいことです。















 また、DJI GS proでミッションを設定してプログラム飛行させ、フォトマッピングをしました。今後は「いろはシステム」で解析を行う予定です。
また、DJI GS proでミッションを設定してプログラム飛行させ、フォトマッピングをしました。今後は「いろはシステム」で解析を行う予定です。